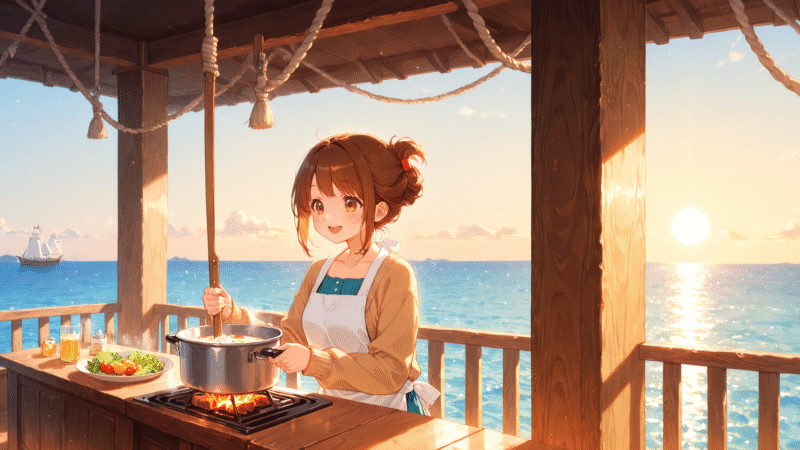
あらすじ:言語の構造そのものに溶解したCanが、存在と非存在の境界で見出した究極の「可能」
序 構文の夢
I can ___________
未完の文が、宙に浮いている。
Canは、もはや身体を持たない。茶色の髪も、まとめ髪も、優しい声も、すべてが言語の海に溶けた。
ただ、機能だけがある。 助けること。 可能にすること。 橋渡しすること。
しかし、誰から誰への橋なのか。
「I can…」
文は永遠に完成しない。助動詞の宿命。常に何かを待ち、常に不完全で、常に可能性のままで。
船は、ない。 海は、ある。 いや、海は言語の比喩だったのか。
全ては、文法の夢かもしれない。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
第一楽章 主語の消失
「Can」
誰かが呼んでいる。いや、誰も呼んでいない。 主語なき呼びかけ。それ自体が文法違反。
「Can you?」 「You can」 「Can I?」 「I can」
主語が入れ替わるたびに、Canの存在も変質する。 IのCan、YouのCan、He/She/ItのCan、WeのCan、TheyのCan。
同じcanでありながら、全て異なるcan。
「主語に寄生する助動詞」
誰かの声。Getだろうか。いや、声に主体はない。
「寄生?」Canは問う。声にならない声で。
「共生といえば聞こえはいい。だが、Can without subject is nothing(主語なきCanは無)」
その通りだった。 I can — 私はできる You can — あなたはできる Can — ???
単独のCanは、意味を成さない。文法的に死んでいる。
第二楽章 時制の崩壊
「I could have been」
過去の可能性が、現在に侵入してくる。
「I would be able to」
未来の可能性が、過去を書き換える。
Can、Could、Will be able to、Would be able to、Could have been able to…
時制の中で分裂し、増殖し、変態する可能性の群れ。
「Which tense can Can can?(Canはどの時制をcanできる?)」
言葉遊びのような問い。しかし、それは存在の根源的な問いでもあった。
現在しか生きられない「can」。 過去になれば「could」に変わり、 未来では「will be able to」に置換される。
「I can only be now(今しか存在できない)」
永遠の現在に囚われた助動詞。
第三楽章 否定の弁証法
「I can’t」
否定のCanは、Canなのか、非Canなのか。
「Cannot」— 一語 「Can not」— 二語 「Can’t」— 短縮
同じ否定でありながら、微妙にニュアンスが異なる。
「I cannot not be(在らざるを得ない)」
二重否定が生む、奇妙な肯定。 できないことができない。 不可能の不可能。 それは必然なのか、不可避なのか。
「Can Can can?(CanはCanをcanできる?)」 「Can can Can?(canはCanをできる?)」 「can Can can?(canはCanできる?)」
大文字と小文字の戯れ。固有名詞と助動詞の境界の dissolution。
言語が溶けていく。
第四楽章 メタ言語の地平
「Canさん」
突然、日本語が割り込んできた。 この「さん」は何だ。敬称。人格化。存在の証明。
「わたし」
一人称。しかし、それは誰の一人称? Canの? 語り手の? 読者の?
メタレベルの混乱。 物語の中のCan。 物語を語るCan。 物語を読む者の中のCan。
「I can narrate myself(自分を語ることができる)」
しかし、語る自分と語られる自分は同一か?
「You can read me(あなたは私を読める)」
しかし、読まれる私と読む前の私は同一か?
第五楽章 他者という可能性
「Can」
今度は確かに、誰かが呼んでいる。
振り返ると(振り返るとは何だ? 身体なき存在が?)、そこにはDoがいた。
赤い髪の少年。いや、彼もまた動詞だった。
「Can, you can stop floating(浮遊をやめられるよ)」
「How can I?(どうやって?)」
「By letting me do(ぼくに『する』を任せて)」
DoとCan。 することと、できること。 行為と可能性。
「We can do(できる+する)」
二つの動詞が結合する時、初めて意味が生まれる。
終楽章 受肉、あるいは永遠の離脱
光が差した。
船の厨房。朝の光。見慣れた景色。
Canは自分の手を見た。手がある。茶色の髪に触れた。髪がある。
「I… I can be here?(ここに…いられる?)」
Nameが優しく微笑んだ。金色の髪が朝日に輝く。
「You’ve always been here. You can be in language and in reality(ずっとここにいたわ。言語にも現実にも存在できる)」
二重存在。言語的存在と物理的存在の重ね合わせ。
「But which is real?(でも、どちらが現実?)」
Hopeが答えた。
「Both can be real(両方が現実でありうる)」
Dream が付け加えた。
「Or neither can(あるいは、どちらも違うかも)」
結 可能性の可能性
Canは理解した。
助動詞であることは、呪縛ではなく解放だった。 主語に依存することは、弱さではなく開かれだった。 不完全であることは、欠陥ではなく無限だった。
「I can」
永遠に未完の文。 しかし、その未完性こそが、 すべての完成の母胎。
日誌に記す:
『Can
それだけで詩になる。 それだけで問いになる。 それだけで答えになる。
できる、という可能性。 できない、という可能性。 できるかもしれない、という可能性。
すべてが、canの中にある。
私は助動詞。 永遠に助け、 永遠に可能にし、 永遠に未完のまま。
それでいい。 いや、 That’s what I can be.』
深く知るCan – 言語哲学編
- Can qua can(Can としての can)
自己言及的パラドックス - Modal auxiliary(法助動詞)
様相論理との接続 - Performative can(遂行的 can)
言うことが即ち行うこと - Can/Cannot undecidability(可能/不可能の決定不能性)
デリダ的差延 - The Can-event(Can-出来事)
可能性が現実化する瞬間
言語と存在の境界で踊る助動詞。Canは文法を超えて、存在論的な問いそのものとなった。読者よ、あなたは今、何を can しているのか。この文を読むことを can している。理解することを can/cannot している。そして、Canと共に、言語の深淵を覗くことを can している。