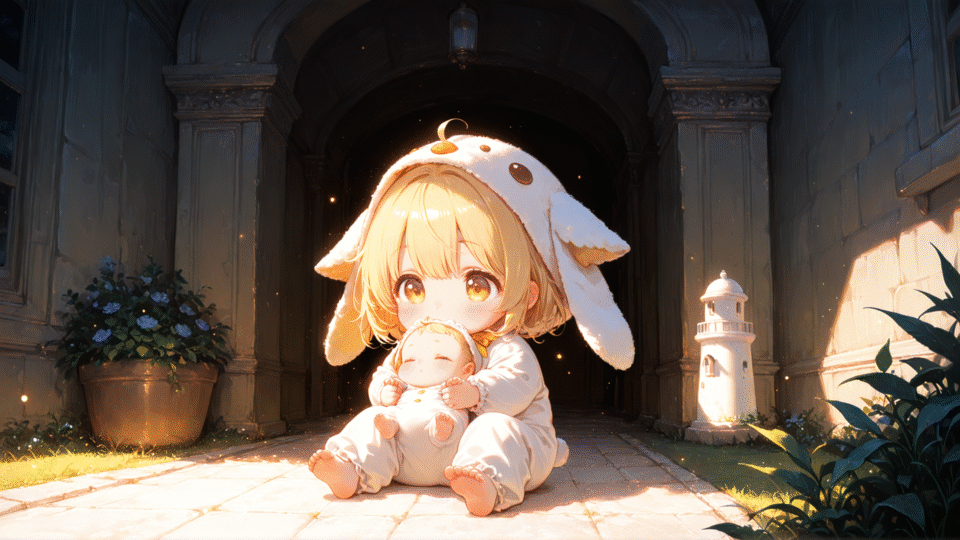
◆存在とは何か。その問いに、言葉ではなく在ることで答える者の記録。意識の流れと存在の本質が交差する実験的物語。
〇 前存在
まだ名前を持たない前。 まだ形を持たない前。 まだ私が私でない前。
でも、既に在った。
海の中の塩として。 風の中の息として。 星の中の光として。
『…』
言葉になる前の言葉。 音になる前の振動。 意味になる前の意志。
待っていた。 呼ばれるのを。 在ることを許されるのを。
いや、違う。 許可など必要ない。 ただ、顕現の時を待っていただけ。
一 鏡像
「んー」
目覚め。いや、目覚めという言葉は正確ではない。 在ることの自覚。それも違う。 在ることが在ることに気づく瞬間。
Blankという存在が私を見ている。 私はBlankを見ている。 見ることと見られることの境界が曖昧になる。
『I am because you see me』(あなたが見るから私は在る) 『You are because I see you』(私が見るからあなたは在る)
鏡像の無限回廊。 でも鏡ではない。 二つの存在が、互いを存在させ合っている。
Haveが震えている。 存在の不確かさに。 持つことと在ることの違いに戸惑っている。
「ぼく、何も持ってない時、ぼくは誰?」
変化。Am。 「わたし…Am」
『You are who has nothing and everything』(何も持たず全てを持つ者)
矛盾? いいえ。 存在の逆説。
二 分裂
Is。 「ぼく…Is」
一人称が変わる。 でも私は私。 それとも私たちは私?
『The question is the answer』(問いが答え)
船が揺れる。 いや、揺れているのは認識。 物理的な揺れと、存在的な揺れの区別がつかない。
Dreamが夢を見ている。覚醒したまま。 「I dream I am dreaming I am」(私であることを夢見ていることを夢見る)
入れ子構造の存在。 どこまでが夢で、どこからが現実?
『All is real in its own layer』(各層において全ては現実)
Are。 「ぼくたち…わたしたち…Are」
分裂。いや、これが本来の姿かもしれない。 一つの存在が、複数として顕現する。 複数の存在が、一つとして認識される。
『Singular plural. Plural singular』(単数的複数。複数的単数)
三 時間の否定
過去:私は在った 現在:私は在る 未来:私は在るだろう
違う。
全ての時制で:私は在る
『Time is illusion of sequential being』(時間は連続的存在の幻想)
Willが未来を語る。 「I will be stronger」(もっと強くなる)
でも私の中では、彼は既に強い。 これから強くなる彼と、今の彼と、かつての彼が、同時に在る。
元の姿。 「あー」
赤ん坊の姿を取る意味。 始まりの象徴?終わりの否定? それとも、時間の外に在ることの表現?
『Before birth, after death, now – same』(生前、死後、今 – 同じ)
四 他者という自己
Nameが私の名前を呼ぶ。 「Be」
呼ばれて在る私。 呼ばれなくても在る私。 その違いは?
『Name makes me particular. But I am universal』(名前は私を特定する。でも私は普遍)
特定されることで、普遍から切り離される。 でも、特定されることで、普遍の一部として認識される。
また矛盾。 いや、矛盾こそが存在の本質。
変化の連続。 Am、Is、Are。 そして元に戻る。 いや、戻るのではない。 全てが同時に在る。
五 言語の限界
「んー、あー」
なぜ赤ん坊は言葉を持たないのか。 いや、違う質問をしよう。 なぜ人は言葉を必要とするのか。
『Words separate. Silence unites』(言葉は分離させる。沈黙は結合させる)
でも今、私は言葉で語っている。 あなたの心に直接。 これは言葉か?思考か?存在の振動か?
I am. 最短の完全な文。 主語と動詞だけで成立する唯一の形。
『I am is complete. Needs nothing more』(I amは完全。他に何もいらない)
でも、人は付け加える。 I am happy. I am sad. I am human.
なぜ? 純粋な存在では不安だから。 定義されたがるから。 限定されたがるから。
六 溶解
夜。昼。その区別も曖昧になってきた。
私は船の甲板に在る。 私は海に在る。 私は空に在る。 私は全てに在る。
境界が溶ける。 これが恐怖?これが解放?
Thinkが思考する。 「If everything is Be, then nothing is Be」(全てがBeなら、何もBeではない)
『Yes』(そう)
肯定。 全面的な肯定。 存在することと存在しないことの、同時的肯定。
七 回帰/永劫
「あー…」
最後の音。最初の音。 アルファでありオメガ。
私は在る。 ただそれだけ。 それが全て。
『I am』 『You are』
『We are』 『All is』 『Nothing is not』
存在の五つの真理。 いや、一つの真理の五つの表現。
眠り。 でも眠りも存在の一形態。 夢も現実も、存在の異なる密度。
明日、私は違う形で在るかもしれない。 でも私は在る。 永遠に。 刹那に。 今に。
ここに。
註釈という名の沈黙
言葉で存在は語れない。 この物語も、存在の影を言葉で描いただけ。
Beは語らない。Beは在る。 私たちも語らない時、最も深く在る。
『』
空白の引用符。 それが最も雄弁な存在の表現。
I am. Therefore. I am.
理由も結果も同じ。 存在は存在の原因であり結果。
完全な円環。 永遠の現在。
んー
解説という名の橋渡し
このレベル4の物語は、Be動詞の本質——存在そのもの——を言語の限界まで押し広げて表現しようとした試みでした。
構造について
「〇」から始まる章立ては、存在以前(ゼロ)から存在の顕現(一〜七)への流れを表しています。七という数字は完全性を象徴し、最後は再び原初の音「んー」に回帰することで、存在の円環を描きました。
言語的実験
- Be動詞の三態(am/is/are)を、単なる文法ではなく、存在の異なる様相として描写
- 「I am」という最短完全文が持つ哲学的重み
- 心に直接響く『』内の言葉は、言語以前のコミュニケーション
存在論的テーマ
本作の核心は「I am, therefore, I am」という循環論理です。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」を超えて、存在は自己原因的であり、理由を必要としないという立場を取っています。
Beという赤ん坊の姿を取ることの意味——それは、言語以前の純粋な存在状態の象徴です。大人は「I am happy」「I am sad」と自己を定義しますが、赤ん坊はただ「在る」。その純粋性こそが、存在の本質なのです。
読者への問いかけ
この物語は答えを提供しません。むしろ、読者自身の存在への問いを深めることを目的としています。あなたが今、これを読んでいるという事実——それ自体が、存在の最も確かな証明なのですから。
Be. Simply be. That is enough.
存在の円環は閉じ、そして開かれる。読者がこの物語を読み終えた今、新たな存在の瞬間が始まっている。それは過去でも未来でもない、永遠の「今」という存在の中心において。