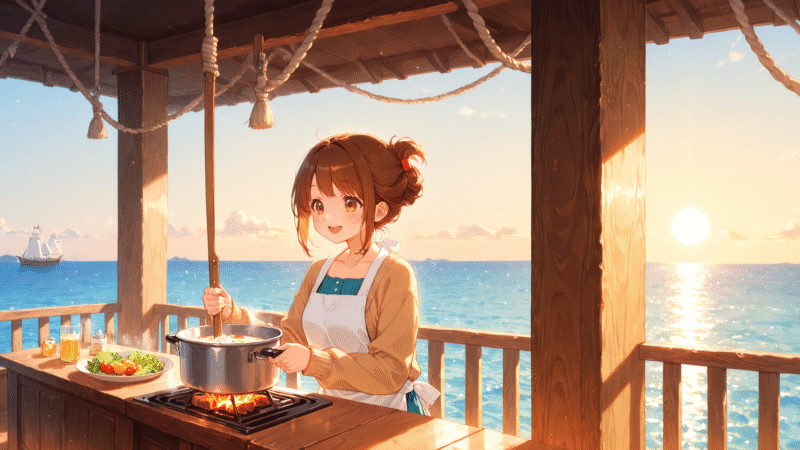
あらすじ:「できる」の本質を極限まで追求したCanが、助動詞としての存在の意味を問い直す物語
第1章 朝の儀式、あるいは機能の檻
午前4時30分。
船がまだ眠りの中にある時刻、Canは既に厨房に立っていた。茶色の髪を一糸乱れぬまとめ髪にし、呼吸さえも計算されたリズムで動く。
「I can predict everyone’s needs(みんなの必要を予測できる)」
包丁が野菜を切る音。リズミカルで、機械的で、完璧。
だが、その完璧さの中に、ある種の虚無があった。
「I can… I can… I can…」
呪文のように繰り返される助動詞。自分は「can」という機能そのものになってしまったのではないか。
Doの好きな卵料理。Nameの苦手な香辛料。Blankの必要カロリー。
すべてを把握し、すべてに応え、すべてを可能にする。
「But can I stop?(でも、止まることはできる?)」
包丁を持つ手が、初めて震えた。
第2章 鏡像の中の対話
昼、Getが厨房を訪れた。その黒い瞳には、いつもと違う光があった。
「Can、君は『できる』を体現している。でも、それは君自身なのか?」
「What do you mean?(どういう意味?)」
「君は助動詞だ。主語じゃない。いつも誰かの『できる』を支えている」
Getの指摘は鋭かった。
「I can only exist with others(他者とのみ存在できる)」
「そう。でも、Can can be Can?(Canは、Canでいることができる?)」
文法的に奇妙な問い。しかし、その奇妙さこそが核心を突いていた。
助動詞は単独では存在できない。常に動詞を必要とする。
「I… I can’t be alone(私は…一人にはなれない)」
「それは弱さ?それとも強さ?」
Getは答えを待たずに去った。残されたCanは、自分の手を見つめた。
この手は、誰かの「できる」のためにある。それは呪縛か、使命か。
第3章 限界の先の領域
嵐が近づく夕暮れ、Dreamが不思議な提案をした。
「Canさん、『できない』ことをやってみない?」
虹色の髪が風に踊る。
「I can’t fail on purpose(わざと失敗はできない)」
「本当に? それとも、won’t(したくない)?」
canとwillの境界。能力と意志の境界。
Dreamは続けた。
「You can choose not to can(『できる』をしないことを選べる)」
パラドックス。助動詞が自己を否定する瞬間。
その時、Canは理解した。「できる」を選ばないことも、一つの「できる」なのだと。
第4章 存在の浮遊
真夜中、Canは一人甲板に立っていた。
星空の下で、自分の存在が透明になっていく感覚があった。
「I can dissolve(溶けることができる)」
Name、Hope、Dream、Blank、Have、Get、Do…
みんなの中に溶けて、みんなの可能性になる。それが助動詞の宿命。
「Can!」
Blankの声で我に返る。
「君は、君のままでいい」
「But I can only be through others(でも他者を通じてしか存在できない)」
「それの何が悪い?」Blankは微笑んだ。「We all can only be through others(みんな他者を通じてしか存在できない)」
関係性の中でのみ存在する。それは弱さではなく、人間の本質。
第5章 崩壊と再生
翌朝、Canは倒れた。
過労でも病気でもない。存在の疲労とでも言うべき何か。
「I can’t can anymore(もう『できる』ができない)」
みんなが心配そうに見守る中、Hopeが言った。
「Can、君は『できる』を独占しすぎた」
Canの代わりに、みんなが動き始めた。
Doが料理を作り(下手だけど)、 Nameが片付けをし(不器用だけど)、 Haveが材料を用意した(多すぎたけど)。
「We all can(みんなできる)」
その光景を見ながら、Canは涙を流した。
「I thought only I could(私だけができると思ってた)」
「No」Dreamが優しく言った。「You can let us can(私たちに『できる』をさせることができる)」
第6章 新しい地平
数日後、Canは変わっていた。
相変わらず料理を作り、みんなを支えている。しかし、何かが根本的に違う。
「I can be uncertain(不確かでいられる)」
「I can watch others can(他の人が『できる』のを見守れる)」
「I can’t, and that’s okay(できない、そしてそれでいい)」
ある夕暮れ、全員が甲板に集まった時、Canは言った。
「I can finally understand(やっと理解できた)」
みんなが耳を傾ける。
「『Can』は可能性の扉。でも、開けるのはみんな自身」
「You can see possibility(可能性が見える)」
「You can share ability(能力を分かち合える)」
「You can be vulnerable(傷つきやすくていい)」
「You can transcend can(『できる』を超えられる)」
最後の言葉は、哲学的な響きを持っていた。
「できる」を超える。それは「できる」に囚われないこと。
終章 助動詞の詩
月光の下、Canは日誌を開いた。
『助動詞として生きること。 それは、永遠に主語になれないこと。 しかし、すべての主語の可能性になれること。
I can — 未完の文。 常に何かを待っている。 その不完全さこそが、無限の可能性。
できることも、できないことも、 すべてが人生の構成要素。
Can can’t. Can’t can.
この矛盾の中に、真実がある。』
ペンを置き、Canは深呼吸した。
明日もまた、誰かの「できる」を支える。 でも今度は、自分も支えられながら。
「We can be(私たちは、在ることができる)」
それ以上でも、それ以下でもなく。
深く知るCan – 哲学編
- Can as possibility(可能性としてのCan)
ハイデガーの可能存在との共鳴 - Cannot not(〜せざるを得ない)
二重否定が生む必然性 - Can be(ありうる)
存在の様態としての可能性 - Could have been(そうであり得た)
過去の可能性への郷愁 - The capacity to incapacitate(無能力化する能力)
アガンベンの潜勢力概念
助動詞の宿命を背負いながら、Canは可能性の本質を体現した。主語になれない存在が、すべての主語の可能性となる逆説。それが、Canが見出した存在の詩学だった。