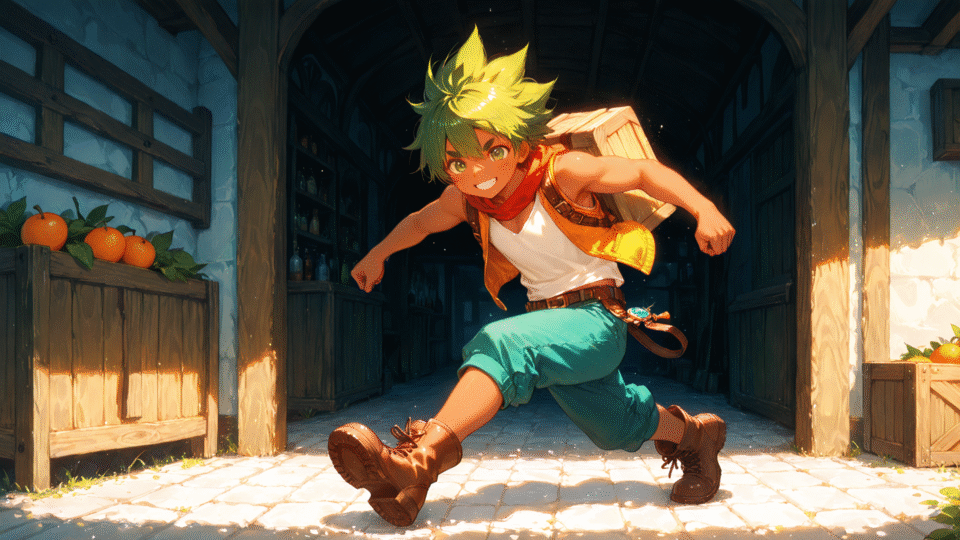
◆言語と存在の狭間で、Takeが「取る」という動詞の限界と可能性を探求する哲学的物語
序章 手の中の虚無
Takeは自分の手を見つめていた。褐色の、がっしりとした手。何度も何かを掴み、何度も何かを離してきた手。
深夜の甲板。他の者たちは眠っている。波の音だけが、執拗に船体を叩く。
(オレは一体、何を取ってきたのか)
手を開く。何もない。 手を握る。やはり何もない。
To take is to believe in the illusion of possession(取ることは、所有という幻想を信じることだ)。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
第一楽章 鏡像としての他者
朝。 Giveが現れた。彼女の金色の髪が、朝日に透ける。
「Take」 「なんだ」 「昨日、あなたが取ったものを覚えてる?」 「パン、ロープ、時間、そして…」 「そして?」 「分からない」
Giveは微笑んだ。その微笑みには、哀しみが潜んでいた。
「You took my trust(私の信頼を取った)。But can trust be taken, or is it only given?(でも信頼は取れるものなの?それとも与えられるものなの?)」
Takeは答えられなかった。言語が、その区別を曖昧にしている。英語のtakeは、日本語の「取る」「受け取る」「奪う」「得る」すべてを内包する。
この多義性こそが、人間の本質的な暴力性を隠蔽しているのではないか。
第二楽章 盗むことの形而上学
昼。 港町。市場の喧騒。
子どもが、リンゴを盗もうとして捕まった。 商人が怒鳴っている。子どもは泣いている。
Takeはリンゴの代金を払った。 子どもは走り去った。礼も言わずに。
「なぜ助けた?」Needが問う。 「I took away his hunger(彼の飢えを取り去った)」 「いや、You took away his chance to learn(彼の学ぶ機会を奪った)」
どちらが正しいのか。どちらも正しく、どちらも間違っている。
Every act of taking is simultaneously an act of giving and depriving(すべての取る行為は、同時に与える行為であり、奪う行為である)。
商人の前にはコインが残された。 子どもの手にはリンゴが残された。 Takeの心には、空虚が残された。
第三楽章 言語の牢獄
夕刻。 Thinkと議論になった。
「『Take』という単語には、なぜこれほど多くの意味があるのか」 「言語が現実を構築するのか、現実が言語を要請するのか」
We take meaning from words, but words take meaning from us(我々は言葉から意味を取るが、言葉も我々から意味を取る)。
Takeは悟り始めていた。自分の名前そのものが、存在論的な問いだということを。
「オレは『Take』だ。でも、I don’t know what I am supposed to take, or what is supposed to take me(何を取るべきなのか、何にとられるべきなのか、分からない)」
Thinkは静かに答えた。 「Perhaps, to take is to be taken(おそらく、取ることは、とられることだ)」
第四楽章 円環の中で
深夜。 再び一人。
Takeは海を見つめる。 海は何も取らない。ただ、与えられたものを返すだけだ。 波は、取っては返し、取っては返す。
Eternal return of taking and giving(取ることと与えることの永劫回帰)。
ふと、Questionが現れた。今は老婆の姿をしている。
「Who are you?(あなたは誰?)」 「I am Take」 「No. Who are you when you are not taking?(違う。取っていない時のあなたは誰?)」
沈黙。
長い、長い沈黙。
「I am… nothing(オレは…無だ)」 「Then, what gives you the right to take?(では、何があなたに取る権利を与えるの?)」 「Nothing… Everything…(無が…すべてが…)」
終楽章 解体と再構築
朝が来る前の、最も暗い時間。
Takeは理解した。 『取る』という行為は、世界を分断する。 ここにあるもの、あそこにあるもの。 私のもの、あなたのもの。
But what if taking is just a temporary disturbance in the flow of being?(しかし、取ることが存在の流れにおける一時的な撹乱にすぎないとしたら?)
Beが現れた。赤ん坊の姿で。 言葉はない。ただ、存在している。
Beは何も取らない。ただ、ある。 その完全性の前で、Takeは崩れ落ちそうになった。
「I… I want to stop taking(もう…取ることをやめたい)」
Beは微笑んだような気がした。 そして、心に直接響いた。
『To stop taking is to stop being Take. Are you ready to take that risk?(取ることをやめることは、Takeであることをやめることだ。その危険を取る準備はあるか?)』
皮肉だった。 取ることをやめるという選択すら、「取る」という動詞で表現される。
結語 浜辺にて
夜明け。
Takeは浜辺に座っている。 手には砂が握られている。 指の隙間から、砂がこぼれ落ちていく。
This is taking(これが取るということだ)。 This is losing(これが失うということだ)。 This is being(これが在るということだ)。
We take breath, we give breath. We take life, we give life. We take death, we give death.
(我々は息を取り、息を与える。 我々は生を取り、生を与える。 我々は死を取り、死を与える。)
In the end, what remains to be taken?(最後に、取るべきものは何が残るのか?) Perhaps, the courage to let go(おそらく、手放す勇気だろう)。
But even letting go is a form of taking – taking the decision, taking the responsibility, taking the consequences.(しかし手放すことさえ、取ることの一形態だ – 決断を取り、責任を取り、結果を取る)
The paradox remains(パラドックスは残る)。 The question remains(問いは残る)。 Take remains(Takeは残る)。
Empty-handed(空手で)。
存在論的註釈
「Take」という動詞は、西洋形而上学の中心的問題である「所有」の概念を体現している。ハイデガーが「手元存在」と「眼前存在」を区別したように、「取る」という行為は、世界を道具的連関の中に配置する。
この物語/反-物語は、言語の限界と可能性を同時に示す。我々は「取る」という言葉なしに世界を語ることはできないが、その言葉によって世界から疎外される。Takeという存在は、この逆説そのものの擬人化である。最後の「Empty-handed(空手)」は、禅の「空」の概念と、実存主義の「投企」を架橋する試みである。何も持たないことで、すべてを持つ。何も取らないことで、すべてを取る。この解決不可能性こそが、人間の条件なのかもしれない。